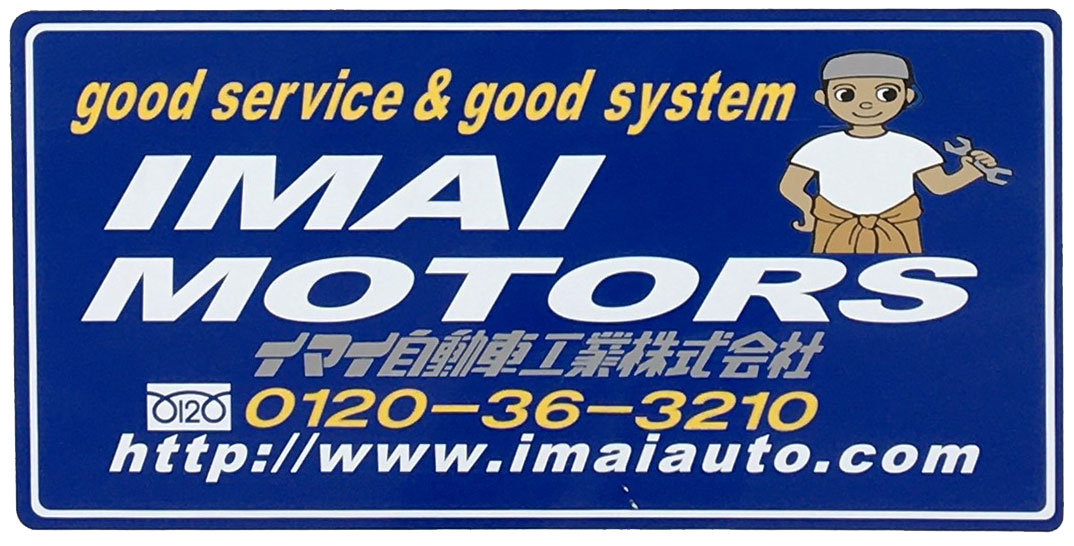ブログ
2025.04.25
長持ちさせる5つの習慣!今日からできるプロのワザ 〜バッテリーは“使い方”で寿命が変わる〜
■ バッテリーは“使い減りする消耗品”
「まだ動いてるから大丈夫」と思って、つい放置しがちなバッテリー。
でも実は、日々の使い方やちょっとしたクセが寿命に大きく影響していること、ご存じでしょうか?
『プロの整備士が実際にやっている5つの“長持ち習慣”』を紹介します。
どれも難しいものではなく、生活の中で意識を少し変えるだけで実行できるものばかりです。
■ 習慣①:週1回、20分以上の「しっかり運転」
エンジンをかけるだけでなく、「しっかり走る」ことが大切です。
バッテリーは『オルタネーター(発電機)』によって走行中に充電されます。
しかし、短距離・短時間の運転では十分な充電ができません。
▷ ポイント
★最低でも週1回、20〜30分以上の走行を習慣にする

★エアコンや電装品を使うときは、走行中に限る
★エンジン始動後すぐに目的地に着くような運転は避ける
「週末しか運転しないんですが、5分くらいの買い物でもダメ?」と質問をいただきます。
5分の運転だと、エンジン始動で使った電力すら回収できないことが多いんです。
すこし遠回りして帰るのも手かもしれません。
■ 習慣②:ライトや室内灯の“消し忘れ防止策”をとる
バッテリー上がりの原因の中でも圧倒的に多いのが「消し忘れ」。
特に、ルームランプやスモールライトの点けっぱなしは要注意です。
▷ 消し忘れ対策のアイデア
★「降車時にライトを目視で確認する」クセをつける
★点灯状態を音で知らせる機能(警告ブザー)を活用
★お子さんが触ってルームランプをつけたままにしないよう注意
【豆知識】
最新車種にはライト自動消灯機能がありますが、完全に頼るのは危険。
たとえば「半ドア状態だとルームランプが点いたままになる」など、例外もあります。
■ 習慣③:停車中は電装品の使用を控える
エンジンをかけたまま、停車中にエアコン・オーディオ・ナビなどを長時間使うと、バッテリーは充電されずにどんどん減っていきます。
とくに夏場・冬場のアイドリング中エアコン使用は、負担が大きくなりがち。
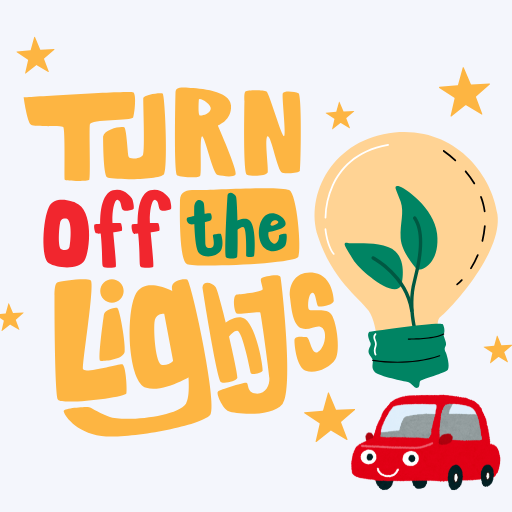
▷ 工夫のポイント
★車内で待機するときは極力エアコンを切るか温度を控えめに
★電装品は“走行中に使う”意識を持つ
★エンジン始動後すぐにオーディオをオンにしない(冷間時はバッテリーが弱っている)
■ 習慣④:定期的に「端子の汚れ」をチェック&清掃
バッテリー端子に白い粉(サルフェーション)やサビが付着すると、電気の流れが悪くなり、バッテリーの性能が低下します。

▷ 清掃の手順
★エンジンを切り、キーを抜く
★軍手をつけて、乾いた布で軽くふき取る
★酢水(中性液)を少し含ませるとサビが取れやすい
★端子には専用の「接点グリス」を塗ると再発防止に◎
ご自分で掃除するの怖いですか?
触るのは感電の心配もない場所なので大丈夫。
とはいえ、不安ならカー用品店で点検してもらえばOKです!
■ 習慣⑤:「補水式」のバッテリーは水量チェックも忘れずに
最近の車は「メンテナンスフリーバッテリー(密閉型)」が主流ですが、
古い車種や軽自動車では補水式(液入りバッテリー)も使われています。

このタイプは定期的な水量確認が必要です。
▷ チェック方法
★バッテリーの上に「LOW」「UPPER」と書かれた透明な窓がある
★液面が「LOW」を下回っていたら、精製水を補充
★水道水はNG(不純物で内部が劣化するため)
■ まとめ:たったこれだけで“バッテリー長寿命化”が叶う!
★週1のしっかり運転→→→十分な充電で劣化予防
★ライト消し忘れ対策→→→不意の上がりを回避
★停車中の電装使用を控える→→→不要な消耗を防ぐ
★端子清掃→→→通電効率アップ&トラブル予防
★水量チェック(補水式)→→→ 電解液不足による劣化防止
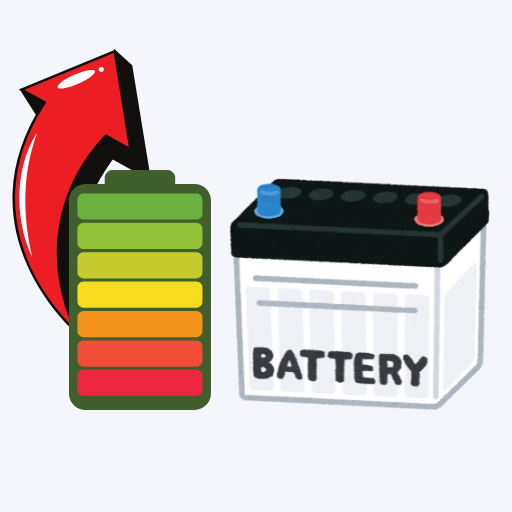
バッテリーは高価なパーツです。
交換頻度を減らすだけでも、数万円単位の節約になることも。
「気にかけるだけ」で車の健康寿命も、あなたの安心もグッと伸ばせます。
◆+ 。。+◇+ 。。+◆+ 。。+◇+ 。。+◆+ 。。+◇
■工場長からのワンポイントアドバイス
■ 次のブログは:「交換のサイン」これを見逃すな!プロの判断基準
「交換すべきかどうか」を判断するポイントを紹介します。
バッテリーを無駄に交換しないために、「プロが注目している“3つのサイン”」をわかりやすく解説します!